![]()
アラジン社(イギリス)
(1930年初頭~)
厳しい寒さが続く今年の冬、多くの時間を室内で過ごす方に、アラジン社の石油ストーブ「ブルーフレーム」をご紹介いたします。
日本では、昭和32年に株式会社ヤナセが輸入販売し、一部の上流家庭で愛用され始めました。その後、昭和35年に「暮らしの手帳」に掲載され、一躍脚光を浴び、急速に普及していきました。それ以降、日本で安全に使用するために、何度も改良され、根強い人気を誇っています。
「ブルーフレーム」の名前にもあるように、このストーブの特徴は、美しい青い炎です。
この青い炎は、ムラなく気化された灯油が、充分な酸素を供給され、良い燃焼状態にある証拠です。嫌な風や臭いもなく、隈なく部屋全体を暖めてくれます。
暖炉の赤い炎とはまた違う心地よさで癒しの空間を演出してくれます。
置いているだけでもおしゃれですが、点火すると、部屋全体がやわらかく心地よい雰囲気になります。
イギリスには大切なものを何台にも受け継ぐ風習があります。
親から子へ、大切なものを伝えていく気持ち、そんな思いが感じられるストーブです。
暖かい部屋にいると、心も体も癒されます。アラジンを点けた部屋で、読書や会話を楽しんでみてはいかがでしょうか。


![]()

尾形光琳(京都)
(1658年・万治元年 - 1716年7月20日・享保元年6月2日))
新春を迎え、光琳の美の世界にふれて見ましょう。
光琳は京都の呉服商「雁金屋」の次男として生まれ、幼少の頃から美の世界に遊んでいました。雁金屋の経営は破綻していましたが、生来遊び人であった光琳は、遊興三昧の日々を送り、相続した莫大な財産を湯水のように使い果たし、40代になって画業に身を入れ始めました。
当時のファッションの先端だった呉服商に生まれた光琳ですが、少年時代から能楽、茶道、書道などに親しんでいたという環境も画風に大きく影響したと思われます。光琳特有の“美意識”は“アマチアリズム”ならではのものであろう、従来の規制概念にとらわれる事なく、感じたものを"特有の技法“で表現しています。この“紅白梅図屏風”に見られる、真中に描かれている流れの表現などは、現代アートつまり“モダンアート”にも通じるものです。
古典を学びながら、常に新しい試みに挑戦し続けた光琳が残した軌跡は、今の時代においても学ぶことは多いのではないでしょうか。
![]()
ノーマン・ロックウェル(アメリカ合衆国・ニューヨーク)
(1894年2月3日-1978年11月8日)
今回は、サンタクロースを題材にした作品を紹介します。作者は、「古き良きアメリカ」を代表する画家・イラストレーターのノーマン・ロックウェルです。ロックウェルは、ニューヨークで生まれ、ゴールドラッシュ、南北戦争、世界大恐慌‥‥そんな自由と開拓、そして激動するアメリカの上流家庭に生まれました。美術学校に進み、様々な経験をする中で、解剖学や感情表現、そしてイラストレーションの意味をひとつひとつ吸収していきました。この作品は、彼が22才から40年に渡って続けられた「サタデー・イブニング・ポスト」誌の表紙を飾った中の1つです。
ロックウェルは、生涯に2000を超える作品を描きました。そんな中、最も多く残したモチーフがサンタクロースです。子どもの頃、誰もが信じたサンタクロース‥‥架空の人物でありながら、今でも世界中のアイドルです。クリスマス当日の道順を赤いテープをめぐらせながら決めている姿は、とても愛情深く、親しみを感じます。ロックウェルの作品は、幼い頃の純粋で、夢を持つ心を思い出させてくれます。
「サタデー・イブニング・ポスト」は、ロックウェルを表紙に起用したことで、廃刊を免れたと言われています。彼の描く、包み込むような優しいイラストレーションに、人々は魅了されたのでしょう。不況が続く世の中で、人が必要としているものは、夢を甦らせてくれる心の温かさではないでしょうか。今年のクリスマスが、みなさんや、みなさんの家族にとって心温まる素敵な1日になることを願っています。

![]()
ルーシー・リー(オーストリア・イギリス)
(1902年3月16日-1955年4月1日)
デイム(大英帝国二等勲章)の称号を持つ、ルーシー・リーは、20世紀を代表する陶芸家の一人です。70年近くにもわたる創作活動の中で、多くの作品を作り、独自のスタイルで陶芸の世界に新しい風を吹き込みました。様々な形・色・テクスチャーの器がありますが、今回は、1970年代に制作された朝顔型の器を紹介します。薄く上品で、小さな高台から上に向かって優雅に開いたフォルム。鮮やかで独創的な色彩。編み針を使った掻き落とし手法や、釉薬の様々な展開‥‥。この器から、彼女の生きてきた時代の流れ、精神性の高さが感じ取られます。高潔かつ大胆で、どこか大らかで優しい魅力のある作品です。
「窯を開ける時はいつも驚きの連続」この言葉に象徴されるように、ルーシー・リーの生涯は、つねに瑞々しい驚きと発見に満ちた陶芸制作に捧げられたものでした。ウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれたルーシーは、工業美術学校でろくろの面白さに魅了され、ほどなくその作品は国際的な展覧会で数々の賞を受賞し、高い評価を得ていきます。しかし、ナチスによるオーストリア併合後、亡命を余儀なくされ、1938年ロンドン・アルビオンに移住し、半世紀にわたり制作を続けました。バーナード・リーチら英国初期スタジオ・ポタリーの作家たちが作り上げていた、大陸とは異なる陶芸環境の中で、ルーシーは当時の先鋭的な建築やデザインの思潮とも響き合う独自の様式を確立していきます。
ろくろから生み出されるかたちに色彩と装飾が一体となり、静かでありながらも強い存在感をもつ作品は、ルーシーが制作の中で見出した発見と喜びを鮮やかに伝えています。
現在、各地でルーシー・リー展が開催されています。「芸術の秋」に相応しい、素敵な展覧会に、足を運んでみてはいかがでしょうか。
ルーシー・リー展 公式ホームページ
![]()
柳 宗理(東京・原宿)
(1915年6月29日-現在)
その名の通り、蝶の形をしたスツール。このバタフライスツールをデザインしたのは、戦後の日本を代表するインダストリアルデザイナー、柳宗理です。シンメトリーの美しさと、形の面白さ、肌が触れたときの感触‥‥自ら、長い年月をかけて何度も手作業でプロトタイプを作るという柳宗理。代表作であるこのスツールには、日本の美意識と、西洋の技術が見事に融合されています。構造に着目してみると、2枚の成形合板を組み合わせ、座面の下の2つのネジと1本の真鍮が使われているだけのシンプルなものになっています。
柳宗理のデザインは、父親であり、民芸運動家であった柳宗悦の影響を強く受けています。幼いころから身近に民芸があり、彼の「直観力」を育ててくれたと言います。そして、東京美術大学時代、バウハウス帰りの水谷武彦氏の講義を聞き、バウハウスの思想や、ル・コルビュジェの考えにふれ、激しく感動したそうです。卒業後には、コルビュジェのパートナーであるシャルロット・ぺリアンの助手を務めることにより、コルビュジェの基本テクニックを学びました。ぺリアンが、日本で民芸を推進していたこともまた、彼のデザインに大きな影響を与えました。
「デザインは、その国の風土に合うものでなければならない」と彼は言います。パリのルーブル美術館、ニューヨーク近代美術館などに収集されているこのスツールは、まさに世界に誇るジャパニーズ・デザイン。天童木工の技術を持って、何代にも渡り、使い続けることができるこのスツールに、一度ふれてみてはいかがでしょうか。



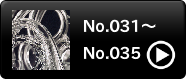
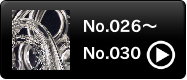
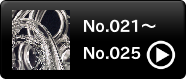
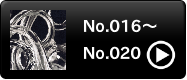
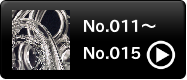
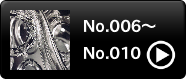
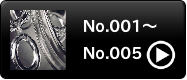





 過去の記事はこちらから
過去の記事はこちらから